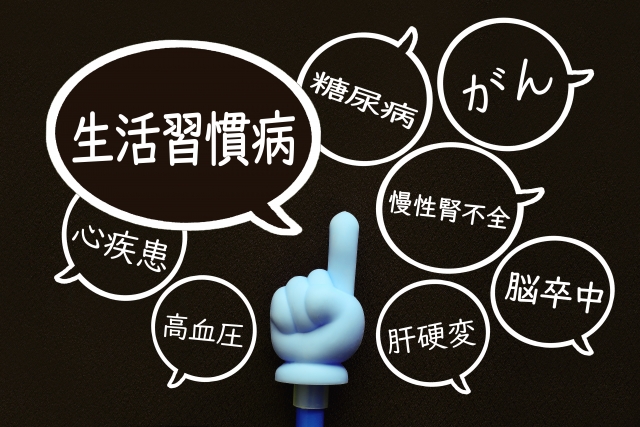2025年10月26日

だんだんと気温が下がってきており、寒さの影響で血圧が高くなり狭心症、心筋梗塞、大動脈解離などの循環器疾患が増える季節となりました。
一般的な狭心症は、ご高齢の方に多く、高血圧、脂質異常症、糖尿病などが原因で「冠動脈」と呼ばれる心臓の血管の壁にプラーク(コレステロールの塊)ができてしまい、血液の通り道が細くなること原因で起こります。典型的な症状は、体を動かしている時(労作)に胸の締め付け感を感じ、安静にしていると症状が治まりますが、再び労作で胸の締め付け感を感じるというもの(労作性狭心症)です。
一方で、思春期から30代の胸痛、胸の締め付けられる感じには状況によってさまざまな原因が考えられますが、ご高齢の方と同じように冠動脈の血液の流れが悪くなる疾患が「冠攣縮性狭心症」です。冠動脈の血管は平滑筋という筋肉でできています。足がつってしまうことと同じように、血管の筋肉が痙攣を起こしてしまう(攣縮)と血液の通り道が狭くなり、心臓の一部に酸素不足を起こしてしまいます。これが原因で胸痛や胸の締め付けられた感じを自覚します。血管の攣縮は、運動時とは限らず、安静時、就寝時、仕事中、運転中など様々な状況で起こります。
血管が痙攣を起こす原因は、遺伝的要因もありますが、生活面では、喫煙、コーヒーなどのカフェインの過剰摂取、精神的ストレス、睡眠不足、寒冷刺激などで、これらが自律神経に影響し交感神経を興奮させ引き起こされます。
動脈硬化が原因で起こる労作性狭心症とは異なり、冠攣縮性狭心症は確定診断が時に難しいことがあります。循環器疾患の多くは、患者さまが自覚症状を感じるときの心電図をみることで初めて確定診断ができます。冠攣縮性狭心症は、自覚症状が一時的であるため、病院を受診された際に自覚症状がなれば診断ができないことがあります。外来でできる検査として最も有効なのは、1日間あるいは3~7日間の心電図が記録できるホルター心電図検査です。長時間の心電図を解析することで診断の精度を高めます。また、自律神経の影響で血管が過緊張状態であり、若いのに血管年齢の上昇を指摘される方も多いようです。
治療法としては、亜硝酸剤やカルシウム拮抗薬の内服を行い症状の改善を確認します。症状に応じて内服の減量や処方の追加を行います。自己判断などでの休薬は、リバウンドを起こす可能性もありますので、減量や休薬の希望があれば必ず医師とご相談ください。